開発エンジニア:エンタメ企業のエンジニアにフルスタックのスキルが身につくのには訳があった
2024.05.24


さまざまなエンタテインメントビジネスを手がけるソニーミュージックグループで、専門的な知識とスキルを持って働く技術者(エンジニア)に話を聞く連載企画。
第6回は、システムエンジニアとしてソニーミュージックグループ内で使用する社内業務アプリケーションの開発コンサルティングなどを行なう岩崎舜に話を聞いた。

岩崎 舜
Iwasaki Shun
ソニー・ミュージックエンタテインメント
──岩崎さんが在籍しているソニー・ミュージックエンタテインメント(以下、SME)のエンタプライズシステム本部は、どのような業務を行なう部門ですか。
売り上げの管理や交通費などの経費精算といった身近なものから、商品別損益計算や情報分析システムまで、ソニーミュージックグループ内の業務で使用するさまざまな社内用業務アプリケーションの開発と保守、運用を行なう部門です。
──市販されている業務アプリも多いですが、一から作っているのでしょうか。
確かに、経費精算や勤怠管理などのアプリは市販のものもたくさんありますが、エンタテインメント会社の業務に合わせたアプリケーションはなかなかないので、一から作ることが多いです。
例えばCDやDVDを製造するときに、その商品は何枚組なのか、またどんなパッケージなのかを記載した仕様書を工場に提出するんですが、そういう業務を円滑に進めるためのアプリは市販のものをカスタムして無理やり使用するより、完全にフィットするものを自前で作ったほうが効率が良いんですね。しかも、ソニーミュージックグループは事業領域が広い分、必要な業務アプリも非常に多く、現時点で170近くあります。
──岩崎さんは、どういったシステムを担当しているのですか。
現在は、「このバンドはこのメンバーで構成されています」「このアーティストの正式表記はこうです」といった、アーティストや楽曲の情報を管理する社内向けのシステムを主に担当しています。
音源、動画素材などの製品情報を管理し、新曲の情報をレーベルのスタッフがデータ登録したら、Apple MusicやSpotifyなどのストリーミングサービスにその情報を届ける。ミュージックビデオの情報が登録されたらYouTubeと連携する。そういったレコード会社と配信プラットフォームの橋渡しですね。
──実際の開発まで行なっているのでしょうか。
開発業務については、外部のITベンダーにお願いしています。私の業務は、ソニーミュージックグループの各事業会社から業務の自動化やシステムの改修について問い合わせや要望を受け、その解決策を一緒に考えるITコンサルティングのような業務というとイメージしやすいかもしれません。業務上、どんな課題を抱えているのかをヒアリングし、それについて「この予算規模であれば、こういったシステムを作れます」と企画、提案しています。
また、その内容を開発会社の方にお伝えするのも私の役割です。ソニーミュージックグループと開発会社のハブになるということですね。
──岩崎さんは、もともとシステム開発に興味があったのでしょうか。学生時代はどんなことを学んでいましたか?
自分は文系出身で、大学では法学部に在籍していました。さらに、公務員を目指していたのですが、試験に落ちてしまって。どうしようかと思っていたときにソニーミュージックグループの募集を見つけて「アニメが好きだし、受けてみようかな」と思いエントリーしました。それが2015年のことです。
──文系出身ということですが、プログラミングなどの専門スキルは習得していたんですか?
いえ、完全にゼロでした(笑)。パソコンは好きでしたが、プログラミングの知識、経験ともになくて。システム開発に関しては、会社に入って一から学びました。
──部門には、岩崎さんのような未経験者がほかにもいるのでしょうか。
やはり大学や専門学校で情報系を学んできた人が多いですが未経験者もいます。
──入社後は、研修などスキルを学ぶ機会はあるのでしょうか。
もちろん研修はありますが、自分の場合は実務を通してスキルを身につけました。例えば「10%だった印税率を15%に修正したい。1時間以内にシステムをメンテナンスしてください」といった案件が降ってくるので、自分で調べて何とか間に合わせる、超実践型の促成栽培でした(笑)。
──“こうすればこうなるだろう”という推論を立てて、論理的に考える力に秀でているんでしょうか?
実をいうと、数学が大の苦手なんです(苦笑)。でも、自分を採用してくれた上長からは「法学部出身者はシステム開発に向いている」と言われていました。上長も法学部出身だったのですが、物事を理論立てて考えるロジカルシンキングが得意だというのが根拠だそうです(笑)。
──岩崎さんが今の仕事でやりがい、楽しさを感じるのはどんなときでしょう。
私は、音楽レーベルで働く人のようにアーティストを直接担当しているわけではありませんが、アーティストの素晴らしい音楽、作品をファンの方たちに届ける一助になれていることにやりがいを感じます。また、そうやって自分が携わった案件をテレビや広告で見たり、配信されているのを目の当たりにしたときは、やっぱりうれしいですね。
内容だったり、スケジュールだったり、ときには難しい依頼もありますが、ソニーミュージックグループのシステム部門は、エンタテインメントを生み出す制作部門の思いを実現するのが仕事なので、できる限り力になれればと思っています。
──関わったなかで、特に印象に残っているプロジェクトはありますか?
ふたつあります。ひとつが、レスペーパーのプロジェクトです。以前ソニーミュージックグループでは、アーティストやクリエイターに印税をお支払いする際、紙に金額を印刷して郵送していたのですが、それが毎月膨大な枚数になっていて。
脱炭素活動、コスト削減、業務効率の改善という3つの観点からペーパーレス化は不可欠だと思い、入社3、4年目に印税の通知をPDFで送信するサイトの制作を企画し、運用までこぎ着けました。
──ペーパーレス化は企業が取り組まなければいけない課題のひとつですが、実際やるとなると大変だったのではないですか?
そうですね。最も苦労したのは、国内では個人情報保護法が改正された時期であったことに加え、海外にも展開するサイトだったので、英語対応が必須なうえに、GDPR(個人データの保護と取り扱いについてEUで規定されている法令)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)など、各国、各地域の法律についても調べる必要がありました。ただ、自分が主導した初めての大規模プロジェクトだったので、やりがいも大きかったです。
──もうひとつのプロジェクトは、どんなものでしたか?
音源・画源管理システムの改修プロジェクトです。以前のシステムは、CDやDVDに特化したものでしたが、近年はパッケージ商品を作らず、配信のみで展開することも増えています。そこで数年前、システムを大幅にリニューアルすることになりました。
その際、開発コストを抑えるために、初めて海外の開発会社に依頼したのですが、システム自体が十数年前に作られたものなので、この機能がどうして必要なのか、どうして今こうなっているのかを理解してもらうのが大変で。
さらに、長年使われてきたシステムであるからこそ、リニューアルが改悪になってしまってはいけないので、どうやってより使い勝手の良いものにするか。そこを詰めていくのもかなり難航しました。自分は、このプロジェクトには途中から参加したのですが、開発会社のあるベトナムまで行き、苦労しながらもみんなで完遂したので印象に残っています。
──どういった人が、ソニーミュージックグループの社内システムエンジニアに向いていると思いますか?
コミュニケーションを取るのが得意な人ですね。この仕事では相手と同じ目線に立って、しっかり話を聞き、そのうえで物怖じせずに意見を言って、最終的に納得してもらうことが大事なので、プログラミングのスキル以上に、調整力、ディレクション力が求められると思います。
あと、好奇心が旺盛であることも大事ですね。ITテクノロジーやシステムはどんどん進化していくので、“これでいいや”ではなく“これもやってみよう”の思考ができる人が向いていると思います。
──エンジニアとして、エンタテインメント業界で働く楽しさはどんなところにありますか?
一番は、好きなものに囲まれて仕事ができることです。自分はアニメが好きなんですが、グループ会社のアニプレックスに関わる仕事もありますし、身の回りに最新のエンタテインメントがあふれているのはやはり楽しいです。
それと、これはエンタテインメント業界というよりは、ソニーミュージックグループの文化なのかもしれませんが、言われたことをやるだけなく、自分でやってみたいことを企画立案すると、後押ししてくれる環境があるのも楽しいところだと思います。
「こういう事業効果が見込めるので、こういったシステムを作りましょう」と提案して、そのシステムによって事業に貢献できるのが、やりがいにつながっています。ちなみに、内容面でも予算面でもしっかりハードルが設けられていることもお伝えしておきます(笑)。
──依頼を受けるだけでなく、生み出す仕事もあるんですね。
そうですね。既存のシステムのなかには、相当古いものもあって。私が今まさに関わっているのも、稼働から30年経ったシステムのリニューアル案件です。手が空いているときに、自分から「このシステムは、こういう改善が必要なのでリニューアルしましょう」とか、「同じようなシステムが複数あるので、ひとつに統合しましょう」と提案することもあります。
──そういった働きかけのモチベーションはどこから湧いてくるのでしょう。
私自身、改善や効率化が好きな性格なんです。日ごろから事業部門に対してシステムを使った効率化を提案しているのに、自分自身の業務が非効率なのはカッコ悪いじゃないですか(笑)。自分たちの業務をカッコ良くしたいし、古いシステムをずっとメンテナンスしながら使うより、みんながより使いやすいものにしたい。そういう気持ちがモチベーションになっています。
──岩崎さんが入社してから9年が経ち、DX(デジタルトランスフォーメーション)も進みました。日々の仕事において、変化を感じることはありますか?
入社した当時は、「言われたことをやろう」という受け身の雰囲気が部門内にありましたが、今ではこちらから先回りして提案する場面が増えています。システム部門の発言力、提案する領域がどんどん広がっているように感じますね。
その背景には、人手不足やシステム開発費の高騰といった課題があると思います。システムの導入による業務の効率化が求められるいっぽう、莫大なコストをかけてまでそのシステムが必要なのかという投資判断もシビアになっています。言われるがままではなく、会社としてどこに注力して利益を出すのかという経営判断も関わってくるため、システム部門として考えるべきことも増えてきましたね。
──長期的な視点で、どういったシステムが必要かを考える必要があるんですね。
そうですね。昨今はビジネスが変化するスピードが異常に早くて、2年、3年と開発に時間をかけていると、その間にシステムがそのビジネスにマッチングしなくなってしまうなんてことも起こります。
重厚長大なシステムを開発しても、使われなければ意味がありません。今は小さくスマートに作り、必要な機能を継ぎ足していくことが大事です。さらにそれぞれのパーツを独立させ、有機的に組み合わせていくことが求められます。そういうところにも、時代の変化を感じますね。
──ソニーミュージックグループ内でのエンジニアの存在価値は、ますます高まりそうですね。
そうですね。おそらく各事業会社で、システムについて詳しい人材を欲しています。実際、そういう動きが加速していくのではないかと思います。
──岩崎さんの今後の目標、目指すビジョンを教えてください。
自分はコンテンツを作るよりも、コンテンツを作る人をサポートしたいですね。システムに携わっているとグループ全体を俯瞰できるので、事業会社の管理部でシステムに関する知見を生かし、ビジネスを前進させるお手伝いをしていきたいです。
──長期的な野望はありますか?
お伝えした通り、社内では約170のアプリが稼働していますが、システムとして古くなっているものも多く、「1割の機能しか使ってないけど残している」ものや、「同じような機能のアプリが複数存在する」という課題があります。
それらすべてをリニューアルするわけではなく、本当に必要な機能は何か、サブスク型のSaaS(Software as a Service:ネットワークを経由してソフトを利用するサービス)で代用できないか、統合してシンプル化できないかという観点で断捨離をし、より高効率な運用を目指したいと考えています。
あとは、「システムのことは岩崎に聞け」と言われるようになりたいですね(笑)。
文・取材:野本由起
撮影:干川 修
ソニーミュージックグループ コーポレートサイト
https://www.sme.co.jp/

2024.06.27

2024.06.27

2024.06.19
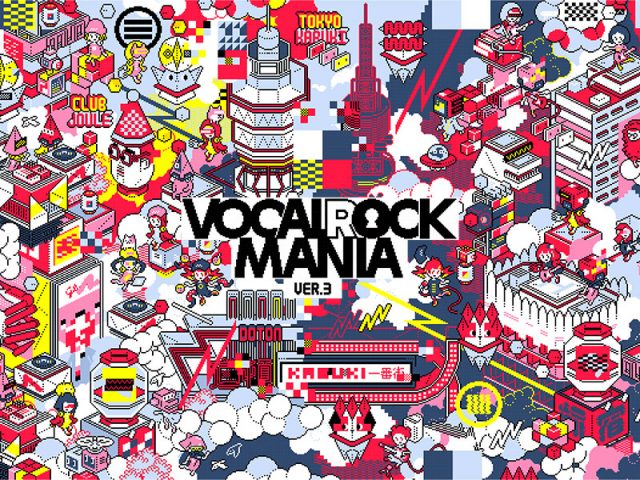
2024.06.05

2024.05.24

2024.05.22
ソニーミュージック公式SNSをフォローして
Cocotameの最新情報をチェック!