子どもたちにエンタメ業界の仕事を知ってもらう教育支援活動――活動を通して伝えたい思い【後編】
2024.06.28


2024.06.27
ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下、SME)では、小中高生を対象にした3つの教育支援活動を展開。2023年度には、地域貢献・共生活動の一環として千代田区立番町小学校の「番町STEAM教育プロジェクト」にも参画した。
次世代を担う子どもたちへ、エンタテインメント会社は何を伝え、どんな体験を提供するのか。教育支援活動を主導するSMEの担当者と「番町STEAM教育プロジェクト」に参加したふたりのA&Rに話を聞いた。前編では、具体的な活動内容、「番町STEAM教育プロジェクト」の手応えについて語る。

灰野一平
Haino Ippei
ソニー・ミュージックレーベルズ

鳥本綾子
Torimoto Ayako
ソニー・ミュージックエンタテインメント

山本秀哉
Yamamoto Shuya
ソニー・ミュージックエンタテインメント
記事の後編はこちら:子どもたちにエンタメ業界の仕事を知ってもらう教育支援活動――活動を通して伝えたい思い【後編】
──皆さんの普段の業務内容、教育支援活動との関わりを教えてください。
鳥本:私は2017年にSMEの広報部に異動となり、それ以降、教育支援活動を担当してきました。
関連記事はこちら:「テクノロジーは企業のCSR活動も進化させるか?」その可能性をエキスパートたちに聞いた【前編】
灰野:私は1996年にソニーミュージックグループに入社し、宣伝、新人発掘、A&R(アーティスト&レパートリー:音楽アーティストをさまざまな面でサポートしながらヒットへ導く音楽業界の業種)などを経て、現在は、ソニー・ミュージックレーベルズ(以下、SML)でgr8!recordsという音楽レーベルの統括を担当しています。
音楽ビジネスを主務としてきたので教育支援活動に関するプロではありませんが、過去には、子どもたちに楽器を身近に感じてもらうためのプロジェクトを経験しました。また、作曲家や編曲家を養成するコミュニティサロン「ソニックアカデミーサロン」の運営にも携わっています。今回、鳥本さんに声をかけてもらって、番町小学校との取り組みに参加しました。
関連記事はこちら:アーティストと二人三脚! A&Rに求められる資質を灰野兄妹に聞く
山本:自分は2012年の入社で、入社直後は現在のソニー・ミュージックソリューションズでCDやゲームのパッケージ製造やデザインを請け負う部署に配属されました。その後、希望してSMLに異動し、現在はA&RとしてYOASOBIなどを担当しています。これまで教育支援活動に携わったことはありませんでしたが、鳥本さんに声をかけてもらって、小学生向けの「遠隔授業」や番町小学校との取り組みに参加しました。
関連記事はこちら:どうしても音楽を作る仕事がしたい――その想いの先にYOASOBIのヒットがあった
──ソニーミュージックグループでは、いつごろからどのような教育支援活動を行なってきたのでしょうか。
鳥本:グループ各社で異なる取り組みを行なっていますが、ヘッドクオーターであるSMEの広報部では、主に3つの教育支援活動を行なっています。
ひとつが、中高生を対象に修学旅行の行程のひとつや総合学習の一環として、学生の皆さんを本社にお招きする「会社訪問プログラム」です。こちらは2000年から始まった取り組みで、ソニーミュージックグループやアーティストのドキュメンタリー映像を通して、A&Rや宣伝、営業など音楽業界のお仕事がどのようなものかをお伝えしています。
プログラムにはグループワークも含まれているので、コロナ禍が発生した2020年からはしばらく休止していましたが、昨年に再開。現在は週2回のペースで実施しています。
会社訪問プログラムの詳細はこちら
ふたつ目が「出張授業」です。こちらは原則、関東圏の中学校、高校を対象にしていて、2010年からNPO法人企業教育研究会の皆さんとともに取り組んでいます。企業教育研究会のサイトから申し込んでいただいた学校に我々が訪れ、音楽業界やアニメ業界のお仕事についてお伝えしています。
こちらもコロナ禍で一時休止していましたが、昨年から「音楽業界の仕事について」のプログラムを再開しました。
3つ目が、一般社団法人 プロフェッショナルをすべての学校にの皆さんと2019年から取り組んでいる、地方や島しょ部在住の小学5、6年生を対象にしたオンラインプログラム「遠隔授業」です。
「遠隔授業」では、まず音楽がどのように作られているかを学んでいただき、“アーティストをプロデュースしよう!”という課題に取り組んでもらいます。現在は、課題楽曲のキャッチコピーや衣装を考え、ポスターにまとめるという課題をお願いし、発表時には教室とオンラインでつながり、子どもたちがプレゼンを、私たちが寸評やアドバイスを行なっています。
個人的には、エンタテインメントを生み出す現場で働くスタッフのリアルな声を学生の皆さんに聞いてもらいたいという思いもあって、「遠隔授業」に関しては、SME広報のスタッフだけでなく、普段アーティストやクリエイターと関わっているプロデューサーやA&Rにも参加してもらっています。
──それで、山本さんは「遠隔授業」にも参加したことがあるわけですね。
山本:はい。子どもたちには、まず曲を聴き、歌詞を読み込んだうえで、楽曲のテーマについて話し合ってもらいました。その後、誰をターゲットにして、何をどう伝えれば良いのかじっくり考えたうえでポスターを作ってもらい、プレゼンを行なってもらいます。
それを受けて、私がコメントをするという形でしたが、生徒さんたちがしっかり考えてくれたことに感動しましたし、小学生がアーティストや楽曲に対してどんなイメージや感想を持っているのかを聞けることはなかなかないので、自分にとっても貴重な機会でしたね。
──「遠隔授業」がスタートしたのは2019年なので、コロナ禍が始まるより前ですよね。どういった経緯でこの取り組みを始めたのでしょう。
鳥本:ちょうどソニーグループでも教育支援活動の一環として「遠隔授業」に取り組んでいて、ソニーミュージックグループでも取り入れようという話になりました。「会社訪問プログラム」と「出張授業」がコロナ禍で休止になりましたが、不幸中の幸いで「遠隔授業」が継続できたので、事前に仕組みを作っておいて良かったです。
「遠隔授業」は学校のある場所に関わらず、気軽につながれるメリットがありますが、以前「出張授業」の特別プログラムで式根島と新島の中学校に伺ったとき、ものすごい歓迎を受けたんです。そのとき直接顔を合わせて授業を行なうことも大事だなと思ったので、両方をうまく活用する必要があると思いました。特に、生徒数が少ない地域の学校では、とても喜ばれますね。
──鳥本さんは、すべての教育支援活動に携わっていますが、そのやりがいはなんですか?
鳥本:私はもともと教育関連に興味があったので、ソニーミュージックグループ内でエデュケーション事業が発足したときにも参加しました。子どもたちは素直で、反応もダイレクトなんです。キラキラした目で、「どうしてこの会社に入ったんですか?」「仕事のやりがいは?」と聞かれると、私自身も初心に戻ったような気持ちになりますし、SMEの広報だけでこうした活動をしているのはもったいないので、多くのスタッフに参加してほしいと願っています。
──2023年度から始まった番町小学校との取り組みは、どのような経緯で始まったプログラムでしょうか。
鳥本:“灯台下暗し”と言いますか、これまでの教育支援活動は、会社の近隣校との取り組みがありませんでした。そんなときSMEのすぐ近くにある番町小学校の校長先生から会社のお問い合わせフォームにご連絡をいただいて。STEAM教育の一環としてソニーミュージックグループと何か取り組みができないかとご提案をいただきました。
打ち合わせを重ねるなかで、“ものづくりやプレゼンテーションを取り入れたい”という校長先生のご要望を軸にしながら、小学3、4年生を対象に複数回の授業を行なうことになったんです。
──どんな授業を行なったのでしょうか。
鳥本:3年生は本社と学校で、4年生は本社と乃木坂にあるソニー・ミュージックスタジオで各学年2回の授業を実施しました。
3年生の授業は“ものづくり”をテーマに、まずは音楽の歴史を伝えたうえで、YOASOBIの「アイドル」を題材に楽曲やパッケージがどのようにして作られるのか、クイズ形式で子どもたちにも参加してもらいながら、授業を行ないました。授業内容を考える際には山本さんにヒアリングし、楽曲やパッケージ制作時の具体的なエピソードも盛り込んでいます。
また、3年生向けの2回目の授業では、普段遠隔授業で行なっているシンガーソングライター・足立佳奈のプロデュース案を考えるというワークショップを実施しました。
──4年生の授業はどういった内容でしたか?
鳥本:1回目で音楽業界の仕事について学び、2回目は音楽制作アプリを使って、ステキな校歌のフレーズを子どもたちが考えて作る。3回目の授業では、灰野さんに協力をお願いして、スタジオでのレコーディング体験を行ないました。
校長先生からご要望があったのと、こちらとしてもせっかくなら座学だけでなく何かリアルな体験を提供したいという思いがあったので、こうした授業を取り入れました。
──参加した子どもたちの反応はいかがでしたか?
鳥本:盛り上がりましたよね。3年生は「アイドル」を流すとみんなで歌い出して、クイズも一生懸命に答えてくれました。
足立佳奈の楽曲「ココロハレテ」のプロデュース案を考える授業は、普段は小学5、6年生に体験してもらうのですが、3年生でもしっかりしたプレゼンを披露してくれました。それとこのときは、発表の最後に「ココロハレテ」をみんなで合唱してくれるというサプライズもあって、ちょっとウルッときてしまいました。
山本:パッケージ制作について学ぶ授業では、そもそもCDを知らない子も多いんじゃないかと思っていましたが、実際はそうでもなくて。レコードを見せると「お父さんが持ってる」という声も挙がりましたし、凝った仕様のパッケージを見せたら、みんな面白がってくれましたね。音楽を作る工程についても、興味を持ってくれたようでした。
──4年生のレコーディング体験の様子も教えてください
灰野:1クラスをレコーディングするチーム、それをコントロールルームから見学するチーム、スタジオ内を見学するチームの3つに分け、それを回していく形で収録を進めたのですが、なかなか難しい課題でしたね。普段はあまりやらないのですが、スタジオにマイクを8人分並べてレコーディングしました。
──グループでレコーディングを体験できるようにしたんですね。
灰野:はい。ですが、それだけでは面白くないですし、音楽ディレクターの仕事がイメージしづらいと思ったので、レコーディングに挑戦するチームにはあえてオーバーな指示を出し、指示する前とした後の歌唱の変化をコントロールルームで見学するチームに感じてもらいました。
「ここは、優しく歌ってみたら良いんじゃない?」「サビはもっと元気に声を張り上げよう」という表現的な指示と、「テンポが走りすぎているよ」「もうちょっと音程を合わせようか」という技術的な指示をして、それによって歌がどう変わっていくかを体感してもらえたかなと思います。
あとは、コントロールルームで見学している子が、「あの子は勉強ができるんだよ」「あの子はモテるんだ」なんて教えてくれる、小学生ならではの雰囲気も面白かったですね(笑)。スタジオの機材に興味を示す子もいれば、レコーディングのやり方に興味を持つ子、もちろん、何にも興味を示さない子もいて、同じことを体験しても、それぞれの性質によっていろいろな感じ方をしているのが自分にとっては新鮮でした。
──山本さん、灰野さんにとっても、普段のお仕事とはまったく違う体験ですよね。実際に参加して、どのような印象を持ちましたか?
山本:とても刺激になりました。始まる前は、子どもたちがどこまで理解できるのかわからず、この内容でちゃんと伝わるのかという不安もありましたが、思っていた以上に子どもたちには知識があるし、理解力も高くて。きっと日々いろいろな情報に囲まれて、吸収して生活しているんだろうなと思いました。
灰野:自分は、レコ―ディング体験の担当だったので最初から子ども扱いをしないようにしました。大人に意見を求めるのと同じように、「どう思う?」と真剣に聞くようにして、子どもたちがいろいろな発見をする様子を観察するのが楽しかったです。
普段のレコーディングでもそうですが、イメージを伝えることで表現が変わるタイプと、技術的な指示をすることで表現が変わるタイプがいます。ひとつの集団でもそういった違いがあるので、それも面白いなと思いながら見ていました。
──校長先生をはじめ、番町小学校の先生方とはどんなコミュニケーションがありましたか?
鳥本:皆さん本当に喜んでくださいました。レコーディング体験後に先生とお話したのですが、「今回の授業を通して、子どもたちに感謝の心が芽生えました。自分がこの体験に参加できることを、すごくありがたいことだと感じたようです」とおっしゃっていたのが特に印象に残っています。
後編では、担当者たちの教育支援活動に対する思いと今後の展望を聞いた。
文・取材:野本由起
撮影:干川 修

2024.06.27

2024.06.27

2024.06.19
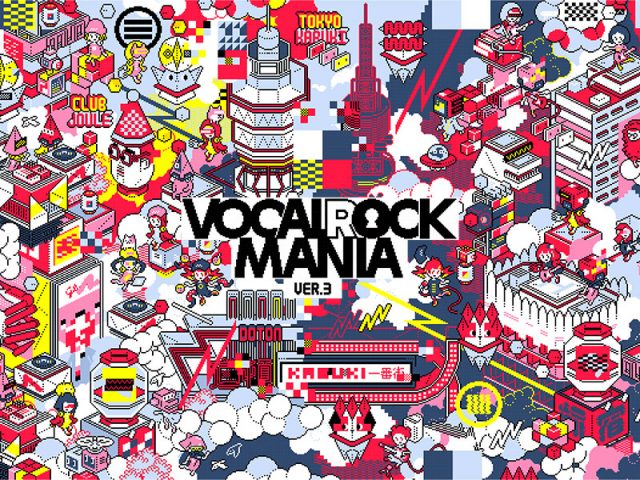
2024.06.05

2024.05.24

2024.05.22
ソニーミュージック公式SNSをフォローして
Cocotameの最新情報をチェック!