良い音でなければ世に出さない――覚悟を決めて挑んだ『MDR-M1ST』開発秘話【前編】
2019.09.09
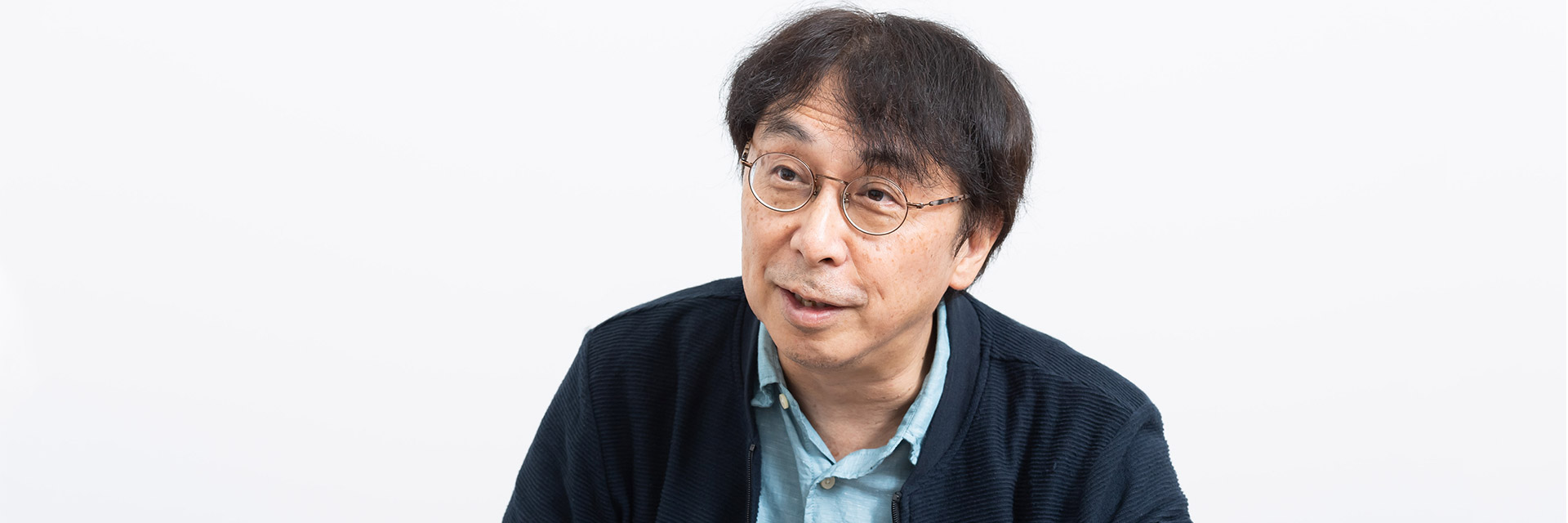

2019.08.22
レコーディングスタジオをはじめ、音作りのプロたちが自らの仕事を磨き、音楽を仕上げるために使用するモニターヘッドホン。そんなプロ御用達のヘッドホンに、新たなモデルが加わる。それがソニーとソニー・ミュージックスタジオが共同で開発した『MDR-M1ST』だ。
ハイレゾ音源にも対応し、これからの音楽制作に必須の新世代ツール。その誕生の裏側には約4年半もの歳月をかけて音を作り込んでいったエンジニアたちの姿があった――。
テクノロジーでエンタテインメントを支える人々を追う連載企画「Tech Stories」では、『MDR-M1ST』の企画・開発から製品化に至るまで、携わった者たちの証言から新時代のリファレンスサウンドに求められた音の輪郭を明確にする。
連載1回目は『MDR-M1ST』の原点にクローズアップ。発売から30年以上が経過した今なお、プロの現場で愛用され続け、モニターヘッドホンの代名詞と呼ばれる『MDR-CD900ST』が生まれた背景を追いながら、『MDR-M1ST』の誕生前夜を照らしていこう。

投野耕治氏
Nageno Koji
ソニーホームエンタテインメント&サウンドプロダクツ
この30年で音楽を取り巻く環境は大きく変化した。メディアはCDの全盛からダウンロード、ストリーミングへと移り変わり、まもなくハイレゾ音源によるストリーミングも本格化しようとしている。レコーディングは、アナログからデジタルへと技術的な過渡期を経て、プロ・ツールスなどのPCを中心としたDTM環境が一般化。インターネットの普及によって音源は瞬時にして世界に届けることができるようになり、クリエイティブの可能性は大きく拡張している。
しかし、モニターヘッドホンの『MDR-CD900ST』だけはそのまま音作りの現場に参加し続けている。2000年以降のヘッドホンブームを背景に、ヘッドホンの音響技術が大きく進化したにも関わらずだ。
『MDR-CD900ST』はなぜ誕生から30年以上が経った今でも、エンジニアからアーティストまで絶大な支持と信頼を得ているのか。ソニーで主にヘッドホンの開発に従事し、数々の銘機をその耳と手で生み出してきた『MDR-CD900ST』の開発者・投野耕治は、ソニー・ミュージックスタジオのスタジオエンジニアたちとともに『MDR-CD900ST』を開発した日々を、「決して平らなものではなかった」と語る。
ソニーとソニー・ミュージックスタジオが共同で開発したモニターヘッドホン。1988年に、CBS・ソニー(現ソニー・ミュージックエンタテインメント)の六本木スタジオと信濃町スタジオで使用されることを目的として『MDR-CD900CBS』という型番で登場。その後、スタジオ業務用専売機として1989年に『MDR-CD900ST』に改番して発売された。一般販売は、1995年から開始されている。
「ソニーのヘッドホンはスタジオでは使えないね。」
1985年にソニーから発売された『MDR-CD900』は、投野が手がけた自信作だ。市場でも高評価だったこのモデルをソニー・ミュージックスタジオのエンジニアに試聴してもらい、返ってきたのがこの言葉だった。
当時、ソニー・ミュージックスタジオでは、藤木電器のヘッドホンを使用。藤木電器は国内で最初にヘッドホンを手掛けたメーカーとして知られ、スタジオをはじめとしたプロの現場でよく使われていた。投野らは、そこに自分たちが開発したヘッドホンを売り込みに行ったのだ。
「我々も一生懸命ヘッドホンの開発をやっていたし、CD時代の新しい音を追求した『MDR-CD900』の音に自信もありました。さらに、同じソニーグループという関係もあるので、すんなり受け入れてくれるのではないかと期待したのですが、まったくもって甘い考えでしたね(苦笑)。」
こうして始まった音のプロたちによる共同の音作り。そんななかで、最初にスタジオエンジニアから受けた指摘は、音の距離感だった。
「リスニング用ヘッドホンに求められる原音というのは、コンサートホールやライブハウスの客席で聴こえてくる音になるわけですが、モニター用の基準になるのはマイクのポジションだということがわかったんです。当時、スタジオエンジニアの方から“10cmの距離感が大事で、それが正確に聴こえなければモニターヘッドホンとしては使えない”と教えてもらいました。」
人間は歌うときも喋るときも、自分の口から出た音を耳で聴き、それをフィードバックすることで声量や音程を調整している。そして、人間の口と耳は平均で約10㎝の距離感となる。そのためレコーディングで、ヘッドホンから聴こえてくる音が近過ぎて刺激的なものだと歌い手はうるさいと感じてしまい、必要以上に柔らかく歌ってしまったり、逆に音が遠くに感じられると声を張り上げてしまうのだ。これは楽器の演奏でも近しいことになる。
一方、この距離感の問題はスタジオエンジニア側にとっても作業をする上で死活問題だった。歌い手の口元からマイクまでの距離が10cmならば、録音エンジニアがモニターヘッドホンで聴いたときには耳から10cmの位置に口があるように聞こえてほしいのだという。さらに、リバーブなどの音操作で空間の広がりを付けたときには、ヘッドホンがその音の変化を表現できなければならない。
これがプロの現場で求められる精度であり、モニターヘッドホンに求められる音なのだ。
「歌い手や楽器演奏者、レコーディング・エンジニアの方の実際の距離感を正しく再現してほしい。それが大前提にあった上で、個々の楽器の音の再現性が求められ、音の立ち上がりや立ち下り、切れといったスピード感、さらには音の重さ、軽さに通じる音色にまで注文があって、とにかくこだわりがすごかったですね。しかし、それは裏を返せばスタジオ側も理想のヘッドホンを求めていたということ。だったら僕らで作ってやろうじゃないかと、開発に着手しました。そして、そこから足かけ3年にわたる開発が始まりました。」
ソニーのエンジニアとソニー・ミュージックスタジオのスタジオエンジニア。音に携わる者同士、理想の音やお互いが抱えるジレンマはスムーズに理解しあえるように思えるが、求めている音の観点の違いに当初は気づかなかったという。
「例えば“ベースの音色を合わせる”という課題があったときに、最初は、低音の切れが悪いよ、声が前に出てないよとコメントをもらって持ち帰り、こういうことかな? と自分なりに理解して調整していました。」
音楽という“音の入り口”を生み出すエンジニアと、ヘッドホンという“音の出口”を生み出すエンジニア。音という視覚化できないものを間に挟さみながら、お互いが培ってきた技術を辞書代わりに、共通言語を手探りする日々が続いた。
「聴いている音源や音量も違うので、どこかちぐはぐしていました。きっとスタジオの方々も何で理解できないのかなと思っていたでしょうね。それで、僕がスタジオの録音現場に行って、彼らと同じ音を同時に聴きながらこの音はこうだね、とコミュニケーションして感覚と言葉をシンクロさせていったんです。そうすることで初めてお互いが話している言葉の意味がわかるようになり、音のイメージを共有することができました。」
共通言語が生まれたことで、投野も自分の感覚で音のチューニングができるようになり、これで一気に開発が進むのかと思いきや、事はそう一筋縄ではいかなかったようだ。
「こちらも音響設計のプロなので、こういう音作りをすれば良いんだと作業自体はスムーズに流れていくようになったんです。でも、スタジオの方々が理想とする音にピントを合わせるのに、結局1年以上かかりましたね。」
何度試作を持ち込んでもダメ出しが飛ぶ。だが、それは音に妥協できないスタジオエンジニアたちの姿勢の表われでもあった。そこは投野もよく理解し、ひたすらチューニングを繰り返す日々が続いた。開発を断念するようなことはなかったのだろうか?
「良いものを作ろうという共通認識がありましたし、スタジオの皆さんは最後まで本当に協力的でした。しかも、音楽や音に対する見識をいっぱい持っていて、音楽が好きな僕には刺激的な日々だったんです。」
音の入り口と出口を結ぶ道は、人が分け入ったことのない山道。しかし、たとえ山頂が見えなくても、音楽があれば進んでいけた。それともうひとつ、投野の背中を押す出会いがあったという。
「『MDR-CD900ST』の開発で、辻 暁さんと一緒にお仕事できたのは一生の思い出です。僕は吹奏楽をやっているのですが、中学のときにCBS・ソニーレコードから『ニュー・サウンズ・イン・ブラス』という吹奏楽のポピュラー編曲の楽譜とレコードが一緒に発売になったんです。それを買って聴いたときに、編曲や演奏の素晴らしさとともに、録音がすばらしいなと感じたんですね。ブラスの輝かしい音色、ハーモニーの煌びやかさ、ダイナミックなリズム感……、吹奏楽のレコードはたくさん聴いていたんですが、そのどれとも違っていました。それで録音を担当した人が気になって、ジャケットの裏を見てみると、辻 暁と書いてあるわけですよ。それ以来、CBS・ソニーレコードのレコーディング・エンジニア“辻 暁さん”という名前が心に刻まれていたんです。」
多くの人が経験したであろう、好きな音楽に没頭する時間と、その音楽を生み出した人への強烈な憧れ。投野は中学生でそれに出会い、15年後、自らの仕事場で再会を果たす。30年以上、音楽制作の現場で愛用されてきた銘機の誕生には、こんなエピソードが隠されていた。
『MDR-CD900ST』が誕生した当時、レコーディングはアナログからデジタルへと移行するタイミングであったのと同時に、低域の音の表現力についても変化が訪れていた。アナログ録音では限界とされ、やむなくカットしていた低域の音がデジタルでは録音できるとわかり、これを使って楽曲を作る傾向が強まっていったのだった。
「アナログ時代は振幅限界があって低音を100%入れることは難しかったのですが、デジタルになると限界がなくなった。一方で、シンセサイザーや打ち込みによっていくらでも低い音が使えるようになりました。これに合わせるようにヘッドホンも極薄フィルム振動板仕様の密閉型で低域を伸ばせるようになったり、スピーカーでもサブウーファーシステムが一般的になってきたりと、低音の再生環境が変わってきたんですね。」
CDの出現によって低域の拡張に限らず、広いダイナミックレンジやより繊細な高音表現など、幅広い音楽表現の変化が可能になり、そういった時代が要請する音にヘッドホンも対応を求められるのは必然だった。
「日本の楽曲でも音の録り方が大きく変わりつつあり、モニターヘッドホンとしても当初は置き換えを目標にしていましたが、最終的にはより従来の音から進化した音作りを目標に開発が進みました。そうやって完成したのが『MDR-CD900ST』です。そういう意味ではうまく継投できたと思います。」
トライ&エラーを繰り返し、3年の歳月をかけて開発が進められたソニー初のモニターヘッドホンだが、エンジニアたちは最後の最後まで妥協を許さなかったという。
「実は最終の音サンプルはふたつあったんです。声がしっかりと聴こえる、やや帯域の狭いモデルと、ハイレスポンスで帯域の広いモデル。スタジオの方たちも意見が分かれてしまって、その中間はないの? なんて聞かれもしましたが(笑)、最終的には5年先を見越すのではなく、10年20年先を考えたときに、どちらがベストかという考えで後者にしました。そういう意味では、30年以上のときを経て新たに加わる『MDR-M1ST』もそういう思考で作られていると思いますよ。」
誕生から31年。『MDR-CD900ST』は今も現役で音楽の現場で活躍し続けている。その最大の要因は何なのか、改めて聞いてみた。
「客観的な評価としては、声の表現力を挙げてくださる方が多かったですね。声に特化したというと極端ですが、確かにその部分は突き詰めました。また、さまざまな楽器があるなかで、それぞれの音色が正確に出てくることも必須条件だったので、そこのクオリティも高めていった結果、プロの皆さんに長く愛用してもらえる完成度につながったのかもしれません。」
それにしても30年以上だ。音楽メディアも移り変わり、フォーマットも進化した。3年の歳月を費やし共通言語もできたのだから、新しいモニターヘッドホンを作ろうという意志はなかったのだろうか?
「僕自身には『MDR-CD900ST』に続くモニターヘッドホンを手がける気はなかったですね。もう一度音作りをするとすれば、そもそも心血を注いで作ったヘッドホンなので、どうしても『MDR-CD900ST』に引っ張られて、近い音になってしまったと思うんです。芸術作品ではないですが、開発者の感性や個性が表われるのがヘッドホンの音作りだと思っています。だから、80年代から90年代、そして2000年代になって音楽表現が変化していくなかで、ソニーの後進たちには新しいモニターヘッドホンを作ったら? とは、ずっと言い続けてきました。31年目でやっと実現しましたね(笑)。」
スタジオでマスタリングされた音をそのまま再生するハイレゾの時代に登場した、新たなモニターヘッドホン『MDR-M1ST』。『MDR-CD900ST』はバトンタッチするわけではなく、これからも『MDR-M1ST』と併用して使われていく。30年で培われた基準としての『MDR-CD900ST』の音は、これからも音作りの現場で指針のひとつであり続けるのだ。その上で投野に良い音の定義を聞いてみた。
「良い音かどうかは、音楽が楽しく聴こえるかどうかだけだと僕は考えています。周波数の数値云々ではなく、それは聴く人の原体験によって違ってくる。その人が体験した音の楽しさをどう体現するかしかないのです。だから良い音というのは、最終的に感性、主観で決めるものだと考えています。ただし、お客様の音の聴き方を共有するなかで、自分の好ましいと思える音を追及する、ということです。」
ハイレゾという新世代音声フォーマットの登場により、待望された新しいモニターヘッドホン。それに応える形で登場する『MDR-M1ST』。取り巻く環境は、『MDR-CD900ST』と似ているように感じる。最後に、モニターヘッドホンの開発を振り返って感じたこと、そして『MDR-M1ST』の真価を聞いてみた。
「スタジオのエンジニアと、ヘッドホン開発のエンジニア、両方の専門家が出会って物作りができるのは、その両方をグループに持つソニーならではだと思います。その上で『MDR-CD900ST』の開発では、その後の商品作りにも生きる貴重な経験をさせてもらいましたし、僕にとってすごく幸せな時間でした。エンジニアとして間違いなくターニングポイントになった製品です。そして、この30年で演奏や技術も含めて音楽の形態が大きく様変わりしました。その変化の裏には、まだまだ進歩の余地がたくさんあると思います。『MDR-CD900ST』は『MDR-M1ST』が登場したので、販売終了になるわけではなく、ともにモニターヘッドホンシリーズとして続いていきます。そして音楽はそれぞれの時代のテクノロジーやトレンドに合わせて変化しています。70年代は70年代の音、80年、90年はそれぞれというように、楽曲には時代の空気感が録音されているのです。僕は、その時代の音は、その時代のオーディオで聴くのが、音楽の作り手たちの想いを再現する意味でも最適だと考えています。その捉え方をしたときに、今まさに登場する『MDR-M1ST』は、『MDR-CD900ST』と同様に時代に求められたヘッドホンと言えるのではないでしょうか。」
『MDR-CD900ST』が開発されなければ、あの名曲、あの名盤は生まれなかったかもしれない。それほどまでに『MDR-CD900ST』が果たしてきた役割は大きい。そして『MDR-M1ST』は、この先駆者の存在なくしては生まれなかっただろう。
次回はいよいよ『MDR-M1ST』をフィーチャーする。『MDR-CD900ST』という圧倒的なレファレンスモデルに対して、何を倣い、何を深化させたのか? 『MDR-M1ST』の開発に携わったソニーのエンジニア、そしてソニー・ミュージックスタジオのスタジオエンジニアに集ってもらい、それぞれが開発にかけた想いを聞く。
文・取材:油納将志
撮影:篠田麦也

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27
ソニーミュージック公式SNSをフォローして
Cocotameの最新情報をチェック!