バーチャルタレントの“卵”たちをサポートし、個性を育てる『VEE』プロジェクト【前編】
2022.07.28


2022.06.21
最初は小さなタネが、やがて大樹に育つ――。新たなエンタテインメントビジネスに挑戦する人たちにスポットを当てる連載企画「エンタメビジネスのタネ」。
今回クローズアップするのは、2022年4月9日(土)に開催されたeスポーツ大会『Sony Creative Cup featuring Fortnite』。同イベントは、バトルロイヤルゲーム『フォートナイト』のクリエイティブモードでデザインされたオリジナルマップ上で、一般参加者やインフルエンサーたちがレースを行なうオリジナルトーナメントだ。大会に合わせて、映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』と『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』の世界観を再現した渋谷の街のマップが作成され、現在も『フォートナイト』クリエイティブモード内で一般公開されている。
本イベントでは、『フォートナイト』ファンとマーベル映画ファン、双方のエンゲージメントを高めるために、どのような施策を行なったのか。ゲーム空間で展開するイベントのあり方、eスポーツイベントの発展性について関係者に聞いた。
後編では話を広げ、国内eスポーツの現状、メタバース空間におけるイベントの可能性について語ってもらった。

福田真澄
Fukuda Masumi
ソニーグループ

川本拓三
Kawamoto Takumi
ソニー・ミュージックソリューションズ
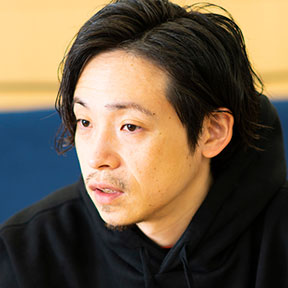
上東鷹介
Kamihigashi Yosuke
ソニー・ミュージックソリューションズ
(前編からつづく)──eスポーツ大会『Sony Creative Cup featuring Fortnite』は、ミレニアル世代、Z世代の方たちがメインターゲットだったそうですが、実際に配信番組を視聴したのは、主にどれくらいの年齢層だったのでしょうか?
福田:一般的なゲームイベントと同じく、10代後半~20代前半の男性層が大半を占めていました。なかでもZ世代の方たちが多かったですね。
川本:SNS上でのコミュニケーションに慣れた方が多かったという印象です。
上東:SNSと親和性の高いイベントは、若年層を狙わないとなかなか火がつきません。若い方が話題にしていると、世代が上の方たちも「それ何?」と気になりますよね。今回は『フォートナイト』が好き=Z世代、ミレニアル世代がメインターゲットでしたし、想定通りの視聴者層を獲得できたのではないかと思います。
福田:映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』と『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』のコアファンはもちろん、今回『フォートナイト』のeスポーツ大会に協賛してもらうことで、特に訴求していきたい10代後半~20代前半の方々に対しても映画をアピールできたのではないかと思います。
──かつては映画を見た人が、「ゲームで『スパイダーマン』の世界が体験できるのか。プレイしてみよう」と流入してくるケースが多かったように感じます。しかし最近では、ゲームを通じて『スパイダーマン』や『ヴェノム』の世界観を知るというケースも増えているように感じます。
福田:コラボカルチャーが浸透し、「自分の好きな作品が別のコンテンツとコラボしたので、そっちもチェックしてみよう」という流れが多くなりましたよね。ゲームで言えば「好きなゲーム実況者が『フォートナイト』をプレイしていたら、自分もやってみたい」と思ったことがあります。また、この現象は低年齢化が進んでいて、SNSやサブスクが生まれたときから存在し、触れてきている世代には、それがコンテンツへのタッチポイントとして当たり前になっています。
川本:例に挙げてもらった通りで、タッチする順番は人それぞれ。先ほどもお話ししましたが、今回のイベントで渋谷の街のマップを作ってくださったクリエイターのヤノスさんは、今回のロケハンで渋谷に来たのが初めてで、ネットの情報をもとに既に完成度の高い渋谷の街を作られていました。ロケハンのときも「ゲームと一緒だ!」と感激していましたからね。僕らからすれば、ゲーム内の渋谷の街を見て「ゲーム内に渋谷の街ができている!」となるのですが、ここでも逆転現象が起こっています。
だから、今回のイベントでも同じことが起きる可能性があると思っていて。イベントを通して『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』を知った方が、そこから映画を見て、過去の作品にまで遡り、さらにマーベルのコミックスを読んでハマっていくこともあると思うんです。特に最近はゲーム空間でほかのIPに触れる機会が増えているように感じますね。
──コンテンツのタッチポイントが増えているということですが、そういった状況のなかで、どうすればファンエンゲージメントを高めるユーザー体験を創出できると思いますか。
上東:自分には中学生の娘がいるんですが、よく彼女や彼女から聞く友だちのコンテンツ消費行動を参考にさせてもらっています。今の中学生たちのタッチポイントは、僕ら世代とはまったく違うので、従来と同じコミュニケーションプランを考えても通用しなくなっていると感じます。しかも、ポストコロナ時代に直面しているので、それに合わせて適切なプランを考える必要があると思います。
今回で言うと、“コミュニティを巻き込んで、遊びながら盛り上がれるeスポーツイベント”をコンセプトに掲げています。従来の映画ファンは、ゲーム空間でTSUTAYAのなかに入り、店頭が『スパイダーマン』と『ヴェノム』にジャックされているのを見て、実際に店舗に来たような気分で楽しめる。ゲームで遊びたい人たちは、タイムアタックに夢中になるうちに、だんだんと『スパイダーマン』と『ヴェノム』が気になっていく。世代によってファンエンゲージメントが違うので、そこをどうカバーしていくか、全体を見ながら丁寧に考えていくことが大事だと改めて思いました。
──コロナ禍ではリアルイベントの代替として、オンラインイベントを開催するケースも数多くありました。ですが、今回のイベントはeスポーツありきです。発想から変える必要がありますよね。
上東:そうですね。リアルイベントと同じことをやっても仕方がなくて。リアルイベントではできないことを実現して、さらにゲーム空間ならではの楽しさを提供することがミッションでした。
もちろんリアルイベントは今も需要がありますし、そちらのほうが適しているということも多々あります。どんなイベントにするか考える上で、軸になるのが“欲求”と“課題”。このふたつは表裏一体です。例えば、コロナ禍で渋谷に遊びに行けないなら、その願望をどう叶えるか。このような個人のささやかな願望も課題と捉え、それらを解決することでエンゲージメントを高めていくという考え方が重要だと思います。
──eスポーツについてもご意見を聞かせてください。日本のeスポーツ市場は、現在どのような段階にあると考えていますか。
福田:ひと口にeスポーツと言っても、タイトルごとに成熟度が違います。eスポーツは、いわば“スポーツ”という大きなカテゴリーと同じ。スポーツにサッカーや野球、バスケットボールなどさまざまな競技があるように、eスポーツもゲームタイトルごとにまったく状況が違うんですね。
成熟しているタイトルもあれば、注目度は高いもののそれ一本で食べていける選手は少ないタイトルもあります。ただ、皆さん驚かれるのは、それだけで食べていけるような成熟したタイトルが国内でも10近くはあるということ。こうしたタイトルになると、トップクラスの選手の収入はかなり高額になります。
──海外では、さらに市場が広がっているのでしょうか。
福田:そうですね。eスポーツで大会が開かれるのは、基本的に対戦ゲームです。格闘ゲームでも、シューティングゲームでも、対戦ゲームが増えていますし、その分eスポーツも盛り上がっています。
川本:あと日本の場合は、プロゲーマーになるよりゲーム実況で動画を配信するほうが稼げる場合もありますね。
福田:ただ、どちらの世界も大きな成功を収めるのは一握りの方たちです。それは、どこの業界も変わりません。
上東:日本にも優秀なプロゲーマーの方はたくさんいますし、それこそ海外で活躍している方もいます。ただ、日本のeスポーツ市場は立ち上がったばかりなので、eスポーツの楽しさが伝わり切っていないのかもしれません。サッカーで例えても、Jリーグができてサッカーの楽しみ方や応援の仕方が浸透し、そこから選手の個性や戦術がわかるようになってサポーターが根付きました。eスポーツは、まだファンの見る目を養っている段階なのかなと感じます。
──確かに画面上で何が起きているのかわからないと、どこが面白いポイントなのか、テクニックとしてすごいのかわからないということはありそうです。実況や解説などを通じて、楽しみ方をわかりやすく伝える必要がありますね。
川本:今回のイベントでも、まさにその点が制作上の課題でした。クリエイティブモードでの対決をどのように見せるか。そして、マップ上のどこにカメラを置いて、どんなシーンを見せるとユーザーの方たちが熱狂するのか。手探りで進めていきましたが、ゲーム内で起きていることをいかにしてひとつの画面のなかで演出していくかという点は、まだまだ改善の余地があると感じましたね。
──今回のイベントでは、マップクリエイターとしてヤノスさん、大会を盛りあげる役としてインフルエンサーの方々を起用していました。新しい才能をキャッチアップするために、どのような情報収集をされていますか?
川本:今回は、福田さんからご提案いただいた方々を起用させていただきました。福田さんはゲームコミュニティに詳しくて、その情報が確かなのでいつも頼りにさせてもらっています。実際、こういう情報は遠いところからリサーチしてもなかなか核心に届かないので、やはりコミュニティのなかに身を置くことが大事なポイントだと思いました。
福田:私は以前からゲームコミュニティを作ったり、コミュニティに参加する活動をしてきたので、ゲーマーの方々とのネットワークも作れていました。だから、ゲーム分野の情報をキャッチするのは、割と早いほうではないかと思います。逆に言うと音楽や映画の分野は全然わからないので、今回とても勉強になりました。
──上東さんは、クリエイターを支援するサービスにも携わっていると聞いています。
上東:はい。運営は、同じグループ会社のソニー・ミュージックレーベルズが行なっていますが、「MECRE(メクル)」というクリエイターのコミュニケーションスペースの立ち上げに参加しました。絵師や歌い手のコミュニティを形成して、そのなかで自由にコラボレーションしてもらい作品を作ってもらう、クリエイター同士のマッチングの場ですね。こちらの活動でも、実際にコミュニティに属している方、その界隈にいる方の意見や要望を聞くことがとても重要だということに気付きました。
川本:ソニーミュージックグループのなかでエンタテインメントのソリューションをビジネスにしている会社、ソニー・ミュージックソリューションズは、そういったコミュニティを提供することも役割のひとつではないかと思います。
上東:個人個人の生き方、働き方が多様化し、さらにSNSの進化によって個の発信力が高まったことで、これから先の時代は、遊びと仕事の境目がどんどん薄くなってくるのではないかと思います。例えば、プロゲーマーの方は“ゲームが好き”という出発点があって、そこを突き詰めていった結果、プロになったという方が多いです。YouTuberの方でも、趣味を発信しつづけた結果、その世界で著名になり、仕事になったという方がいます。
そういう方のほうが“好き”というエネルギーがある分、強いんですよね。自分の好きなものの技術を高めて武器にする。そういう人が力を発揮できる場所が、徐々に用意され始めているということなのかもしれません。
もちろん、遊びや趣味を仕事にすることが楽だとか、楽しいことだらけだと言いたいわけではありません。ただ、働き方の多様性が認められる時代が進むにつれて、遊びと仕事の境界線は確実に曖昧になってくると思います。
だからこそ、我々のようなエンタテインメントの会社は若い人たちが遊べる場、楽しめる場所を作ることがとても重要で、しかも、そこから生まれてくる才能にしっかりアプローチできるようになっていないといけないと思います。
川本:昔はライブハウスやクラブ、ゲームセンターなどが遊び場でしたが、今はそれがオンライン上に無数に存在するんだと思います。
──福田さんは、ビジネスプロデューサーとしてeスポーツに携わっています。『Sony Esports Project』は、現在、eスポーツとどのように向き合っているのでしょうか。今がどういうフェーズなのか教えてください。
福田:『Sony Esports Project』の目的は、eスポーツのプレイヤーやファンの熱量を最大化することです。ソニーグループのさまざまなテクノロジーとIPが融合することで、エンタテインメント性の高いeスポーツ体験をより多くの方に届けたいと考えています。今後もこの目標に向けて、今回のようなeスポーツ大会を開催していきたいです。
──eスポーツで活用できるテクノロジーとは、どのようなものでしょう。
福田:ソニーには、ボリュメトリックキャプチャ技術、バーチャルプロダクション、360立体音響技術など、エンタテインメントをより楽しくする映像や音響のテクノロジーがたくさんあります。まだ実現はできていませんが、こうしたテクノロジーをeスポーツと掛け合わせることができたら面白そうですよね。また、ソニーミュージックグループが得意とするファンエンゲージメントを高めるサービスをeスポーツに導入することも考えられます。
今後も『Sony Esports Project』が持つeスポーツやゲームに関する知見、SMSのデザイン力やソリューション力、若手クリエイターのクリエイティブ力や影響力などを掛け合わせて、eスポーツを盛り上げていきたいと考えています。
──川本さんと上東さんは、ゲーム空間内でのイベント制作という今回の知見を、今後どのようにいかしていきたいですか?
川本:ユーザーの皆さんの熱量を感じる大会にすることができましたし、コンテンツホルダーにとっても作品をアピールする良い機会を創出できたので、こうした形のオンラインイベントの可能性を感じました。とは言えビジネス視点では、マネタイズの部分でまだまだ課題を感じています。今回のような共同プロモーションだけでなく、もっと違う形でマネタイズをする方法があるのではないか。そこはしっかり考えていかないといけないと思います。
上東:私も同意見です。今回はファンエンゲージメントの高いゲームと映画を組み合わせることで、大きな盛り上がりを作ることができました。その検証はできたので、今後はまた違ったコンテンツでもゲーム空間、メタバース空間でのイベントを考えていけたらと思います。
ただ、コンテンツや課題によっては、ゲーム空間でイベントを行なうのではなく、別の施策が向いていることもあります。メニュー化するのではなく、相性や課題に応じてさまざまなイベントのあり方を模索すべきだと思います。
文・取材:野本由起
撮影:干川 修
©2021 Sony Group Corporation ©Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.
© 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2022 MARVEL
© 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2022 MARVEL
『Sony Creative Cup featuring Fortnite』
https://sonyesportsproject.com/event/sony-creative-cup-fortnite/
『Sony Esports Project』
https://sonyesportsproject.com/
『Sony Esports Project』公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UClcoxZ8SsmS1iB0qYG1y_YA
『Sony Esports Project』公式Twitter
https://twitter.com/SonyEsportsPJ

2024.07.24
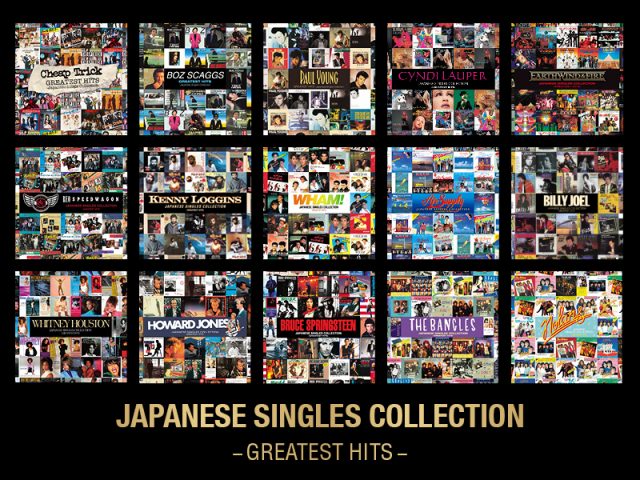
2024.07.23
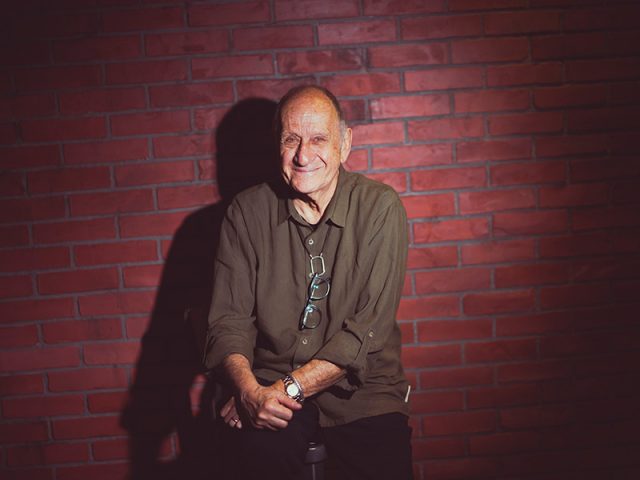
2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27
ソニーミュージック公式SNSをフォローして
Cocotameの最新情報をチェック!